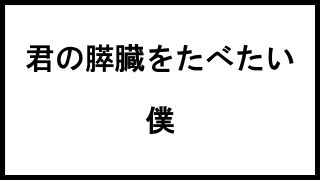「君の膵臓をたべたい」僕(主人公)の名言・台詞をまとめていきます。
君の膵臓をたべたい
クラスメイトであった山内桜良の葬儀は、
生前の彼女にまるで似つかわしくない曇天の日にとり行われた。
たった一言のメール。
これを、彼女が見たのかどうかは知らない。
1
「ずっと考えてたんだ、僕にしては真剣に」
「君のことだよ」
僕はきっとこの道を卒業するまで歩き続けるだろう。
彼女は、あと何度同じ道を歩けるのだろうか。
2
「(言葉を失う?) そうだよ。僕が沈黙しなかっただけでも評価してほしい」
「お金持ちは食べ放題に来ないよ、多分」
「(美味しいのにもったいない?) お金持ちはなんでも食べ放題だよ」
「まかせるよ」
まかせる、というのはなんて僕に似合う言葉だろう。
「(食べたくないの?) 君は膵臓のせいで死んでいくんじゃないか」
「きっと君の魂の欠片が一番残ってる。君の魂はとても騒がしそうだ」
泣くわけがない。
彼女が、人前で悲しむ表情を見せないのに、他の誰かが代行するのはお門違いだ。
「見ようと思えば性別の違う二人組は全部カップルに見えるし」
「外見だけなら君もとても、もうすぐ死ぬようには見えない」
「大切なのは、人からの評価じゃなくて中身」
「馬鹿なのかもしれないとはたまに思うけど、馬鹿にはしてないよ」
「小学生くらいからかな、僕には友達っていうのがいた記憶がない」
「(記憶喪失?) …やっぱり君は馬鹿なのかもしれない」
「人に興味を持たないから、人からも興味を持たれないんだろうね」
「(友達?) いれば楽しかったのかもしれないけど」
「僕は現実の世界よりも小説の中の方が楽しいって信じてるから」
「君みたいな人は、人間関係は複雑だから面白いとか言いそうなものだけど」
「君は僕とは反対の人だから、僕が思いそうにないことを、君が思っているのだろうなと」
「それを口にしたら、当たってた」
3
「本当のことがどうかは、別にどうでもいいんだよ」
「ただ僕はクラスメイト達から観察されるだけならまだしも」
「話しかけられたり詮索されたりするのが嫌だったんだ」
「大事なのは中身だから、誤魔化してもいいんだよ」
「(好きな子?) どんな人、か」
「そうだね、『さん』、をつける人だった」
「中学生の時、クラスにいたんだよ」
「きちんと、何にでも『さん』をつける女の子」
4
僕は一度だけ『共病文庫』について意見をしたことがある。
それは僕の名前について、『共病文庫』に登場させないでほしいということだ。
「(言い訳?) 僕は両親に心配かけないように、友達がいるって嘘をついてるからさ」
「友達の家に泊まるって言うよ」
「(ひどい?) 誰も傷つかないって言ってくれない?」
知っていた、これが現実。
彼女が医学の力で存在を保っているという事実。
目の当たりにすると、心に言いようのない恐怖が降ってくるのを感じた。
押し込めていた怯懦(きょうだ)が、とたんに顔を出した。
僕が知りたいのは、彼女という人間がどうやってできあがったのかということだ。
周囲の人間に影響を与え、影響を与えられる、
僕とは正反対の彼女ができあがる過程を僕は知りたかった。
5
「『さあ』とか『ふーん』とか言われたら」
「その人は君の質問にさほど興味を持ってないんだ」
「(物分かりいい?) 君から学んだんだ」
「草舟は大型船に立ち向かっても意味ないって」
知らなかった、誰かに怒りを向けることが、こんなに誰かを傷つけるなんて。
こんなに自分を傷つけるなんて。
物語の登場人物と、本当の人間は違う。
物語と現実は違う。
現実は、物語ほど美しくもいさぎよくもない。

6
「なるほどね、君の名前にぴったりだ」
「春を選んで咲く花の名前は、出会いや出来事を偶然じゃなく選択だと考えてる」
「君の名前にぴったりだって思ったんだ」
だけれど僕にはその一つか二つを訊く勇気がなかった。
僕という人間は、臆病からできあがっていると、彼女といることで気づかされる。
勇気ある彼女を鏡としてしまう。
「本当に君には、色んなことを教えてもらう」
「本心だよ。ありがとう」
7
たくさん冗談を言って、たくさん笑い合い、たくさん罵倒し合って、
たくさんお互いを尊重し合った。
まるで小学生みたいな僕らの日常が、僕は好きになってしまって、
一体どうしたことだと第三者的な僕が驚いた。
きっとこの世界で一番、人との関わりに感動していた僕の二週間は、
彼女の病室に集約される。
たった四日、その四日が僕の二週間の全てだった。
思わず、僕は一人で笑ってしまった。
そうか僕は、こんなにも変わっていたのか。
違う選択もできたはずなのに、僕は紛れもない僕自身の意思で選び、ここにいるんだ。
以前とは違う僕として、ここにいる。
「僕は、本当は君になりたかった」
『君の膵臓を食べたい』(メール)
8
「ごめんなさい…お門違い、だとは、分かってるんです…」
「だけど…ごめんなさい…」
「…もう、泣いて、いいですか」
僕こそが、今、確信した。
僕は、彼女に出会うために生きてきた。
10
僕らはきっと、二人でいるために生きてきたって、信じてる。
僕らは、自分だけじゃ足りなかったんだ。
だからお互いを補うために生きてきた。
最近は、そういう風に思う。
最後まで読んで頂きありがとうございました。