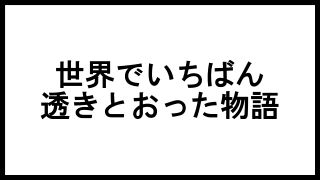「世界でいちばん透きとおった物語(杉井光)」の名言・台詞をまとめていきます。
世界でいちばん透きとおった物語
第1章
「──推理小説にたとえるなら」
「編集者は数多くの証拠を集めてひとつの形にまとめあげる探偵」(深町霧子)
「校正者はその証拠をすべて吟味して裁判に完璧を期する検察官」
「というところでしょうか」(霧子)
「(糾弾?) そうですね。作家をしめきりで追い詰めるのも編集者の仕事です」(霧子)
母が僕に淡い笑みを向けてくるとき、いつも僕はわけもなく哀しくなった。
『泣き顔と笑い顔を入れ替えられてしまった人』みたいに見えるのだ。(藤坂燈真)
(母は)泣くときでさえ、いつも微笑みを浮かべていた。
嬉しい時にしか泣けない人なのだ。(燈真)
だから哀しい時にしか笑えないのだ。(燈真)
母が死んでから一度も泣けないでいる自分は頭がおかしいんじゃないか、と思う。
哀しくないわけではない──はずだった。(燈真)
冷たい雨にずっと打たれていて、
体表は冷え切っているけど身体の芯は熱いのか凍えているのかよく分からない。
そんな感覚だ。(燈真)
時間がたてばあるいは相応の感情もにじみ出てくるものだろうか。
無味無臭の罪悪感がいつもまとわりついていた。(燈真)
第3章
どうせ死ぬとわかっているのなら──見栄も意地も張り続けたまま死ぬ。
そう考える奴がいても不思議じゃない。(燈真)
第4章
ガラケーの中身をあさる作業を、苦く思い出す。
罪悪感で指が凍った。(燈真)
自分が死んだ後にこれをやられたら、と考えると身体のあちこちの粘膜がひゅんと縮む。(燈真)
「先生はね、自分で言ってたんだけど、読書する女ならだれでも口説けるんだってさ」
「逆に読書しない女は頭悪く見えて無理だって」(藍子)
母親のかつての不倫相手が書いた本──なんて、
どれだけ面白かろうが素直に楽しめないにきまっている。(燈真)
僕の中で宮内彰吾は「知らない男」から「よくわからない男」に昇格しつつあった。
いや、むしろ降格か? 上下の問題ではないか。(燈真)
第5章
(母は)死ぬなんて、思ってなかっただろうな。
当たり前だ。僕だって全然思ってなかった。(燈真)
昨日と同じ今日が、今日と同じ明日が、ずっと続くと思っていた。(燈真)
男と女ってそんなに簡単なものなのか。
簡単じゃない部分を説明していないだけか。(燈真)
「なにか伝えたくて小説書いてるわけじゃないよ」
「テーマとかメッセージ性とか、真剣に分析されると笑っちゃうよね」(七尾坂瑞希)
「あんなに色々話してくれたってことは」
「彰吾さんも完成させられないって薄々わかってたからだと思う」(瑞希)
「書き切れる自信があれば、完成まで黙って書き続けるよ」
「作家ならね」(瑞希)
「どんなひどい殺し方でも、実行していないのならなんとでも言える」
「相手への憎悪がそれだけ強かった、という事実の表現に過ぎない」(瑞希)
「ただとにかく、自伝みたいなのとか、過ちの反省とか償いとか」
「そういうつまらないことは書いててほしくないかな」(瑞希)
小説家らしい意見だった。同意できなくもない。
でも、酷な言い分でもある気がした。(燈真)
死ぬその瞬間まで小説家であり続けろ──ということなのだから。
化粧を落とすな、舞台の上で踊ったまま死ねと。(燈真)
第6章
「(他社の利益?) 出版にはあまりそういう敵対意識はないですね」
「売れる本がよそで出ても、自社にとってはむしろ得です」(霧子)
「なんでもするということと、精神的負担を感じるかどうかはまた別問題ですからね」(霧子)
「つまらない改変をされて出版されるくらいなら闇に葬られた方がましですね」(霧子)
「文章はもちろん重要ですけれど、やはりミステリは解決編に至る論理展開が命です」(霧子)
「(勉強?) 読みたいから読む、が小説の幸せな読み方だと思います」(霧子)
呑み込みやすい表現にしようとすると、歯応えの全くない脂身みたいな言葉になる。
といって、深刻すぎないようにと心がけると薄く潰れて吹き飛ばされてしまうのだ。(燈真)
「燈真さんは、言葉で心臓を刺せる人ですね」(霧子)
第7章
自分の親がそんな愚かな人間だとは思いたくなかった。
しかし考えてみれば不倫なんてしている時点ですでに愚かだ。(燈真)
わがままの限りを尽くして周囲に迷惑をかけ続けた父が、最期になにを書き遺したのか、
是非とも見届けてやりたい。(燈真)
好奇心ではないし、父の遺志を汲んでやろうという思いでもない。
もっと下世話だ。(燈真)
瘡蓋(かさぶた)を剥がしたい気持ち、に近い。(燈真)
第8章
「小説って継げるようなものじゃないですからね」(瑞希)
「わたしが考えていたのは『世界でいちばん透きとおった物語』というのが」
「いったいどんな小説なのか、です」(霧子)
「こちらは推論の積み重ねでたどり着ける気がします」(霧子)
「内容がわかっていれば原稿がなくても物語に命を与えられます」(霧子)
「一読者としての共感と、一編集者としての使命感の両方から」
「わたしはその物語を必ず読み手のもとに届けたいんです」(霧子)
『藤坂燈真』という人物の台詞に鉤括弧(かぎかつこ)がつくかつかないか──
くらいの差しかない。(燈真)
第9章
「もし別れたとしても、この人は絶対に私のせいにはしないんだろうな、って思ったら」
「わりとなでも赦せるようになってね」(郁嶋琴美)
「おかげでずっとつきあっていられたんだと思う」
「安心できるって大事だからね」(琴美)

第10章
《母の死んだ日》から離れて季節をぐるりと一巡りし、また近づく。
そのくりかえし。(燈真)
そうして螺旋の上を滑りながら──色んなものをひとつひとつ忘れていくのだろう。(燈真)
第11章
宮内彰吾に怒っていたのではない。ろくでもない男に捕まった母に対してでもない。
怒る相手がいないことに、だろう。(燈真)
第12章
「普通の小説なら意味はないでしょう」
「でも『世界でいちばん透きとおった物語』は、本当に特別な小説なんです」(霧子)
僕を包む世界が軋んですすり泣く。(燈真)
僕の傷はあの男から搾り取った血で埋められ、
あの男から削いだ肉で縫い接がれていたのだ。(燈真)
「宮内先生は小説家でした」
「なにより、ミステリ作家でした」(霧子)
「書こうとした本当の動機は、ただ、面白そうだから」
「読者を驚かせる仕掛けを、思いついてしまたから」(霧子)
「わたしは読んでみたいです」
「燈真さんが書くその物語を、…世界中のだれよりも」(霧子)
第13章
小説を書くという事は祈りに似ていた。
そして他のどんな営みにも似ていなかった。(燈真)
「(作家になれるか?) それだけはわたしにもわかりません」
「一冊読んだだけでは絶対にわからないんです」(霧子)
「この原稿は素晴らしい出来ですけれど」
「処女作で大傑作をものしながら書き続けられなかったという方が、少なからずいらっしゃいます」(霧子)
最後まで読んで頂きありがとうございました。