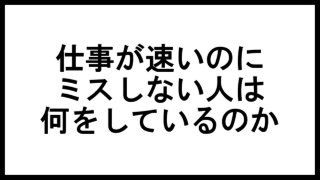「仕事が速いのにミスしない人は何をしているのか(飯野謙次)」の名言をまとめていきます。
仕事が速いのにミスしない人は何をしているのか
はじめに
小さな失敗をきちんと防ぎ、起こってしまったら適切に対処することが、
大きな失敗を起こさないためのたった一つの道である。
1章
ミスは、そのものによる物理的な損失やダメージもありますが、
それ以上に「あなた=ミスをする人」というイメージが、何より恐ろしいのです。
ミスの原因はどこまでも人間にある、という厳しい事実を突きつけてくる反面、
どんなミスでも自分たちの力で防ぐことができる、という希望にもつながります。
失敗学での取り組みを通して見えてくることは、世の中の事故も不祥事も、
「まったく新しいこと」「まったく想定外のこと」が原因で起こることはほとんどない、
ということです。
失敗を防いだり、被害を軽くするためには、
この「過去に必ずヒントがある」という気づきは重要です。
注意力では、失敗もミスもなくすことができない。
人間の絶え間ない高度の注意力を必要とするものがあれば、
それは「作業そのものが成熟していない。作業そのものに設計ミスがある」
2章
ダブルチェックは、1回目のチェックと同じ動作を繰り返すのではなく、
その方法や見方を変えて行うことに意味があるのです。
「たいしたことのないこと」こそリストにして、脳から追い出してしまうこと。
悪いマニュアルとは、ずばり、「わかりにくいマニュアル」です。
正確さにこだわったマニュアルほど、悪い(使いにくい)ものが多い。
マニュアルの目的は、そのしくみ全体を理解することではありません。
より少ない労力で、誰もが正しい手順を辿れることです。
「失敗やミスをなくすコツ」は、実際に失敗が起こったときだけでなく、
何か失敗が起こりそうになったときでも、使うべきだということです。
4章
(メールで)すぐに返せるような内容なのにむやみに時間をかけるのは、
ビジネスパーソンとして失格でしょう。
5章
「知らないこと」にどう対処するかが、
仕事におけるスピードアップとミスの削減に、大いに関連しています。
6章
仕事で人と接するうえで何より大切なのは、
「自分も相手も完全ではない」という前提に立つことです。
最初の段階でうまく信頼関係を結ぶことができないと、
それだけで「失敗」の確率が上がります。

7章
通常私たちが行っている「学習」という形式での「失敗対策」では、
カバーできる失敗がごく限られてしまうのです。
失敗をしたときに、がっかりすることは大切です。
しかし、がっかりするのと気が滅入るのとは違います。
落ち込んでいる暇なんかないのです。
何かがうまくいかないとき、どうしても失敗につながってしまうとき、
必ずどこかに問題点があります。
何度も失敗したことをどうにかして成功させたいときに必要なのは、「小さな諦め」です。
8章
「知らなかった」ということは、失敗の免罪符にはなりません。
仕事で起こる失敗というのは、
「注意不足」「伝達不良」「計画不良」「学習不足」に分析でき、
この4つの原因を取り除けば、個人の失敗に関しては恐れる必要がなくなる。
人間は慣れる動物です。
慣れてしまえば作業が惰性になり、注意力が衰えます。
ですから考えるべきは、「作業が惰性になり、注意力が衰えたとしても、
ミスにつながらないようにするには、どういうしくみをつくればいいか」ということです。
私たちは、計画を間違えたときによく、「考えが甘かった」と反省します。
しかし、これではいつまで経っても計画を立てる能力が向上することはありません。
具体的に何がどう甘かったのか、何の分析もできていないからです。
9章
失敗はたしかに、評価や業績を下げる、なるべくなら避けたいことです。
しかし、してしまった失敗を克服したとき、人は大きな成長を遂げるのです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。